人権って何?どこからやってきたの?
公民の教科書を開くと、
人権(基本的人権)とは、人間が生まれながらに持つ、個人として尊重されながら、平等にあつかわれ、自由に生きる権利のことをいう。
と書いてあります。
しかし、この人権。いつ、誰によって与えられたのでしょうか?
それとも、人類は初めからこのような権利を持って生まれてきたのでしょうか。
困ったときは教科書に戻れ!!と学校の先生は言うけれど。
公民の教科書をどれだけ読んでも、残念ながらその答えは書いてありません。
それでは、どこに書いてあるのか。
実は、私たちは、今まで学習をしてきた歴史の教科書の中で、すでにその答えに触れていたのです。
それがどこに書いてあったか、覚えているでしょうか。
人権とは何ぞや??ということを学ぶ前提として、人権はどこからやってきたのか?について確認をしておきましょう。
近代市民革命という言葉を覚えているでしょうか?
1640年にイギリスで起こったピューリタン革命、1688年から起こった名誉革命などと言えば、記憶にありますか?
イギリスから始まり、フランス革命などヨーロッパ各地に広がったこれらの動きは、市民革命と呼ばれ絶対的な権力を持っていた君主から権利や自由を奪い取っていった出来事です。

国王ってどんなひどいことをしたの?民はなぜそれに抵抗しなかったの?
ところで、国王の絶対的な権力とはどんなものでしょうか?
たとえば、走れメロスに登場する暴君ディニオスは、
「少し派手な暮らしをしている者には、人質一人ずつを差し出すことを命じ」、「命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は、6人殺されました。」
といった具合に、何となくその場の雰囲気でどんどん人の命を奪っていきます。
そんなことが今の時代に起きたら大変ですが、中世の身分制社会とはそういうものでした。
しかし、近代市民革命以前の人々は、なぜこのような暴挙に抵抗せず、甘んじて受け入れていたのでしょうか?
なぜこの時代以降、革命という名の抵抗が可能になったのでしょうか。まずはそこを考えてみてください。
中世と呼ばれる時代、日本でも江戸時代頃までは、人口は現在の10分の1から20分の1です。
あなたのクラスメイトが30人いるとすると、それが、2~3人ぐらいに減るイメージです。
そこまで人が少ないと、日々の生活はどうなるでしょう?
周りは草がぼうぼうで、人はほとんど住んでいない。

しかも生産力はずっと低い。1粒まいたコメや麦がせいぜい10数粒にしかならない。
医療も発達していないため、ちょっとした怪我や風邪でも命を落とす。
飢饉になれば、なけなしの食糧を奪い合って他の村と争いになる。
人々は寄り集まってなんとか生きていくしかない世界。
今みたいに隣には誰が住んでいるか知らず、助け合いといったことをしなくても、個人が勝手気ままに生き、腹が減ったらコンビニで何か買えばいい。
というわけにはいかないのです。
みんなが好き勝手に村を出て畑を耕すことを放棄すれば、全員飢えて死んでしまうので、民は土地を離れることが禁じられていました。
日本でも昔関所というものがありましたが、許可がなければ、関所を越えて別の土地に行くことができないことになっていました。

大学に進学したから、東京に引っ越しますなどということは到底認められなかったのです。
人が生きるということが奇跡であり、無事に明日を迎えられる確率が非常に低い時代においては、偶然偉い人の家に生まれた君主(必ずしも人格的に優れているわけではなくとも)の命令にしたがうことこそが、みんなが生き残る最善の策であり、個人の自由や平等などという贅沢を言える基盤がなかったわけです。
衣食足りて礼節を知る。生産力の向上とともに、個人の自由といった人権感覚が芽生えます。
しかし、少しずつ生産力が向上し、自分で使ってしまっても余る物が出てくるようになると、余った生産物を別の村に持って行って売ろうという人が現れます。
いわゆる商人の登場ですが、山で採れた物は海の集落で高く売れ、海の幸は山の集落の方が高く売れますから、商人は土地に縛り付けられず、自由に移動をして商才を発揮したいと望むことになります。
そして、暴君である支配者の命令がなくても、自分の才覚で生きていける。
それを阻んでいるのは、身分や土地であり、そこから逃れたい、自由にが欲しいと望みます。
現在の日本国憲法の22条1項には
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
と書いてありますが、どこに住むか、どこに引っ越すか、どんな職業に就くかなんて、今の感覚では当然に自由だと思い込んでいるこれらのことも、明治時代になるまでは認められていませんでした。
だから、大切な人権としてわざわざ憲法に明記されているのです。
また、18世紀以降、イギリスから産業革命が起こったことも歴史で学習しましたが、これによって、生産力が飛躍的に向上し、経済的に少し余裕が出てきたことを背景に、
「社会のルールはたった一人の暴君が決めるのではなく、みんなで決めたい。」
「土地や村に縛りつけられるのではなく、まず個人ありき。個人が自分の意思にしたがって生きていくのだ」
という自由を求める考え方が強くなってきました。
そして、この考え方こそが、近代市民革命の原点であり、人権獲得への第一歩だったのです。
まとめると??
人権が、いつ、誰によって与えられたのか?
という問いに対しては、
近代市民革命以降、権力者と国民の闘争によって、民が奪いとっていった
というのが解答になります。
このように、人権は何の苦労もなく、当然に与えられていたものではなく、紆余曲折を経て勝ち取って来たものであり、今後も私たちがそれを守り続けなければならないものであることをよく覚えておいてください。


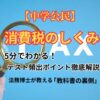
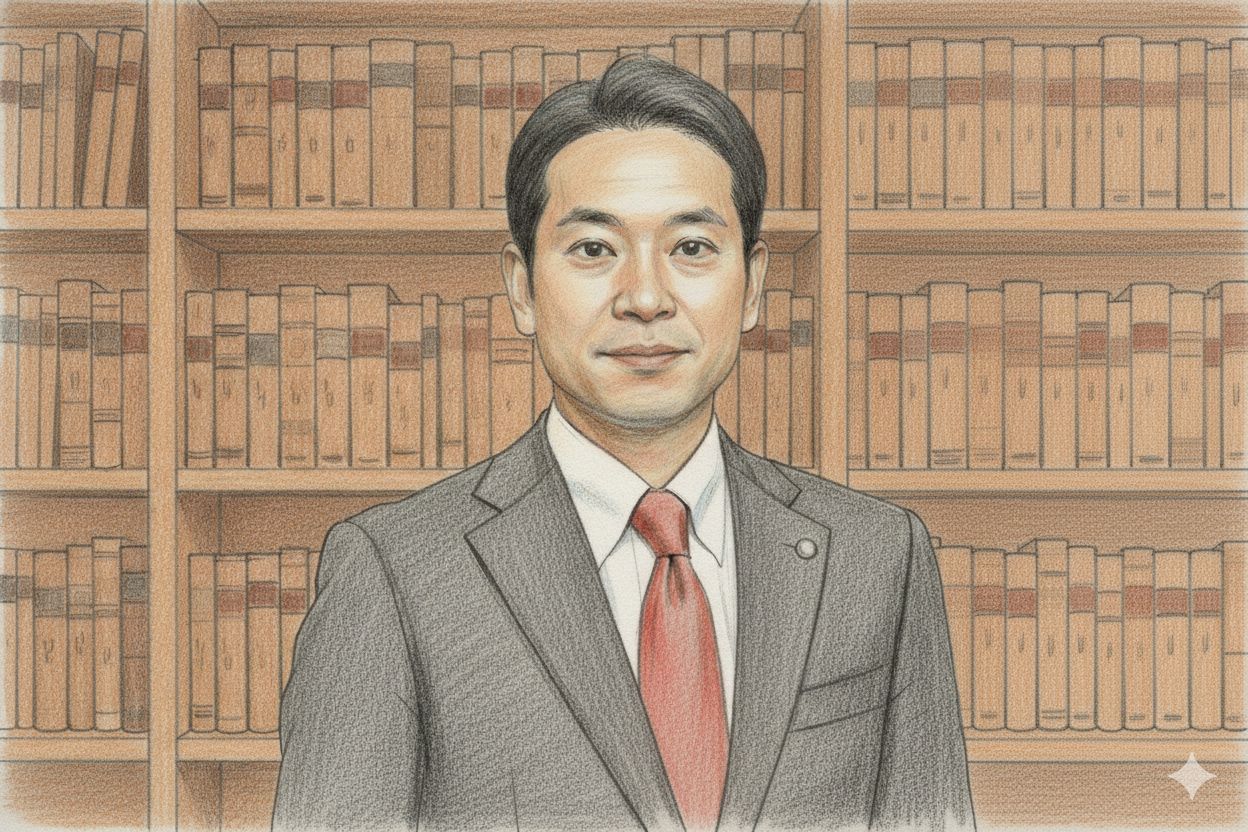
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません